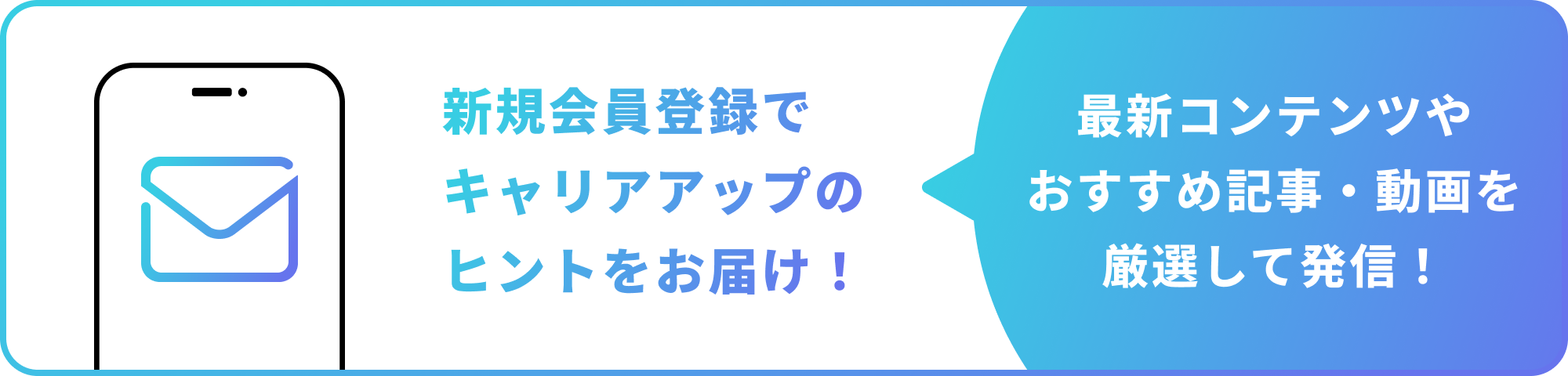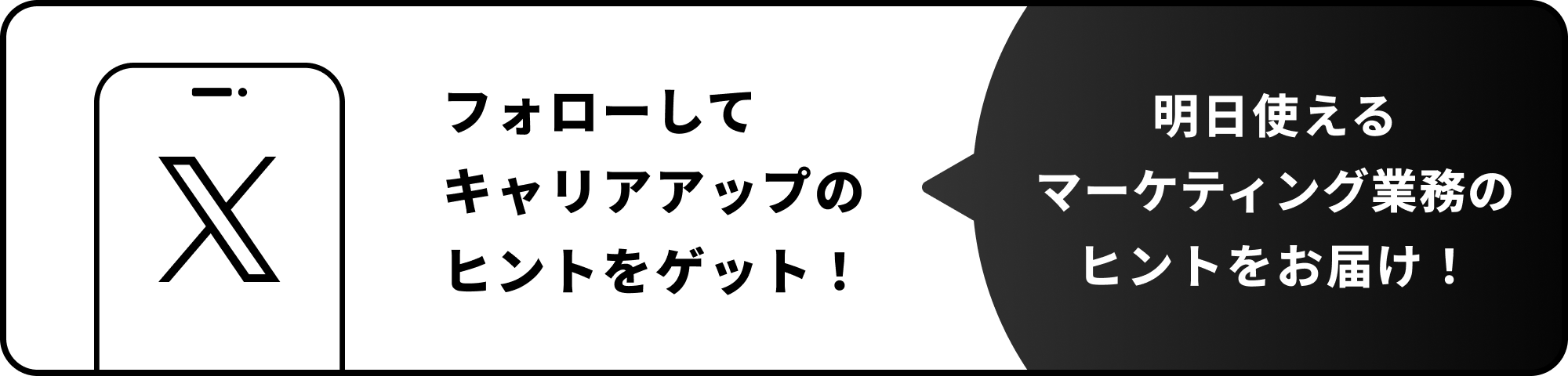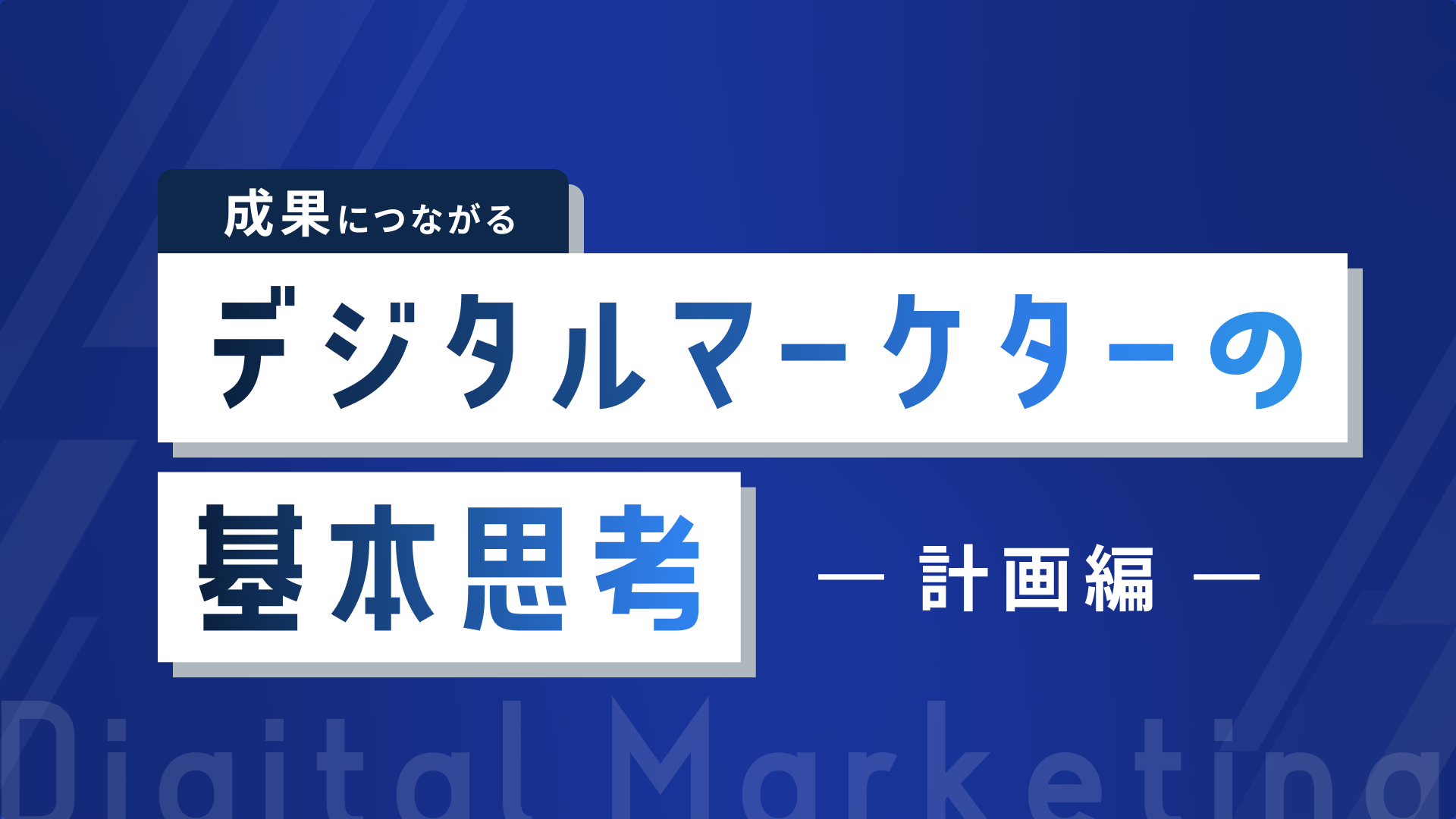食事シーンに応じて意識や目的を使い分けるべし

今日はよろしくお願いします。早速なんですが、松浦さんは普段、どのような食事スタイルですか?
一日三食しっかり摂っています。立場上、決断することが多い役回りなので、食事や睡眠不足のまま考えて間違った判断をしてしまうと、僕だけではなくスタッフや会社全体が損をしてしまいます。
仕事は永遠に続くマラソンのようなものですから、パフォーマンスの持続性を考慮しつつ、かつ時短でしっかり栄養が摂れる食事を心がけています。
スピードと栄養以外で重視するポイントは何かありますか?
日々の食事は、生きていくための栄養をつけるもの、業務をスムーズに進めるために欠かせないものです。それに対し、例えば会食のようなケースだと「場」を意識しています。
会食の席は、基本的に普段会えない方と会って話せる非連続な場になることが多いです。明確なゴールがないおかげで、想像しない観点から話を広げていけるので、想定できないインプットを得るための場所として、意識を変えています。
また、日中の1時間をブロックして行うミーティングなどは、ゴールやトークテーマが決まっていますよね。相手も、ゴールに向けた回答をすることに集中するし、僕は狙った情報を得られる。そんなイメージです。
会食の場所選びって難しい印象ですが、心がけていることがあれば教えてください。
『食べチョク』を運営していることもあり、意図を持ったお店選びをするようにしています。たとえば「こういう生産者の食材を扱っている」とか「こういう旬の食材を使った料理を提供している」などです。
日々の食事では「食べること」に意識を向けますが、会食では「どういう場にするか?」「相手に何を持ち帰ってもらうか?」といったゴールを準備し、それに合わせたシナリオや問いの当て方にフォーカスしています。テーマを設けた店選びをしているのも、そのほうが相手に話題を提供できるからです。
食事の内容よりも、その場をどういったものにするか? に集中しているんですね。
基本的に、会食の席での「もったいない減点」を避けたいと思っているんです。店選びやその場の振る舞いも含め、レベルの高い営業マン的思考を崩しません。そのためにも、場に集まった方々の役職や年齢などは関係なく、「自分がもっとも下っ端だ」という前提で動くようにしています。
休日やプライベートの食事だと、意識は変わりますか?
そこに関してはリラックスする手段で、食事や料理そのものを楽しむことを心がけています。
自炊するときは、献立を決めたり材料を用意したりするところから。外食をするときはお店選びから。時間を気にせずに、自分が楽しむことに重点を置いています。仕事中の食事や会食とは、メリハリをつけるようにしていますね。
効率だけがビジネスパーソンの食事基準ではいけない

仕事の日の食事スタイルについて教えてください。
朝は10分ほどでおにぎりまたはパン、一緒にコーヒーを摂ることが多いです。思考がシャープかつ、まだ人が動き出す前の時間で連絡対応が発生しにくいため、できるだけ早く仕事に取りかかれるようにしています。
昼は移動時間やミーティングのスキマ時間を10〜20分ほど確保して、仕事をしながら摂ります。夜も昼同様で、コンビニで買ったものを会社で食べることが多く、会食が入ることもあります。
具体的に、どんなメニューが多いですか?
ローソンで売られている「1食分の野菜が摂れるポトフ」をよく食べます。「1食分の野菜」っていうフレーズに弱いんですよ。やはり食事で不足しがちなのは野菜なので、1食で十分に補える観点は大事です。
また、体調の波に左右されない点でも、重宝しています。身体にあたたかいものを入れると、仕事で活性化しすぎた頭をほっと落ち着かせる瞬間を作りやすいのもおすすめポイントです。
コンビニ商品で、必要な栄養素を補えるんですね。
もちろん、きちんと栄養バランスを考えた食事を摂るのは大切です。でも、どうしても手間がかかるじゃないですか。

農家で働いている方々も、時間に追われて素早くエネルギーを補給できるコンビニごはんに頼っていることがあります。それは、ほかのビジネスパーソンと変わらない点です。
ほかにコンビニでよく買うものはありますか?
セブンイレブンと「銀座米料亭 八代目儀兵衛」のコラボおにぎりです。ほかのおにぎりに比べて単価は高いんですが、味にこだわっていて、お米や具も良いものを使っているんです。例えば100円多く払うことで、この美味しさを味わえるなら、お得だと思います。
食事を選ぶ基準があれば知りたいです。
基本的には得られる効果をみています。おにぎりやコーヒーなど、毎日同じものを買うにしても、「10円安く買おう」と思うか「100円高くても良いものを食べよう」と思うかの違いです。どちらのほうが、より自分のテンションが上がるのか?僕の場合は、多少高くても美味しさを感じられるほうが、満足度が高いです。
それにくわえて、コンビニなどの大手小売店とのコラボレーション事例は、その手法やブランディングの観点からも学びになります。ブランドとしての見せ方だったり、裏側でどんな施策が走っているのかを想像したり。積極的にコラボレーション商品を買っているのは、新しい取り組みに対して応援したい気持ちもあるからです。
意図を持った食事選びが学びにつながる

松浦さんにとって、食事とは?
一言で表すと「選択の練習ができる機会」です。食事は、いわば年間を通して1000回以上もある「PDCAをまわすチャンス」と捉えています。
学びを得るための食事なのか、心身をリラックスさせる休息の場なのか。食事に求める効果や位置付け(目的)などを定めた上で、意図的に選ぶことが大事だと思います。フワッとしたまま、なんとなく時間が過ぎてしまうのはもったいない。回数が多いからこそ意図を持って選んだほうが、得られる学びの質が高くなるはずです。
なるほど。
とくに食事は、ハイブランドの洋服や鞄などとは違い、少し努力するだけで高品質なものに触れられます。SNSで話題になっているお店を調べたり、街を散歩しているときに行列ができているお店をチェックしたりするだけでも、「味」以外から学べるものがたくさんあります。一流のものに触れるハードルがもっとも手軽なのが「食」ではないでしょうか。
複数の選択肢かつ回数があるからこそ、自分なりの意図を持って選ぶこと。食に「ラベル付け」をすることで、経験の質が高まります。今日や明日から、すぐに意識できることだと思うので、ぜひ次の食事から「何のためにこれを選んだのか?」を考えてみてはどうでしょうか。
この記事に登場する人
松浦 悠介
さん
株式会社ビビッドガーデン 執行役員・事業開発
一橋大学を卒業。学生時代には4社のベンチャー企業でインターンシップを経験し、アジアで初となる新卒でのテクニカルトレーナー職として外資系IT企業のVMwareへ入社。2018年11月にビビッドガーデンに入社し、マーケティング統括として「食べチョク」の成長を牽引。社内初のテレビCM放映プロジェクトを全体統括するなど、マーケティングの責任者として「食べチョク」のグロースを担当。
SNS・メディア
この記事をシェア
ハッシュタグから記事を探す
カテゴリから記事を探す
トップランナーおすすめの良書
トップランナーが見た動画
インタビュー・対談
PERSOL MIRAIZのキャリアコンテンツ
キャリアに活かせる学習動画
トップランナーから、仕事に直結するスキルを学ぶ