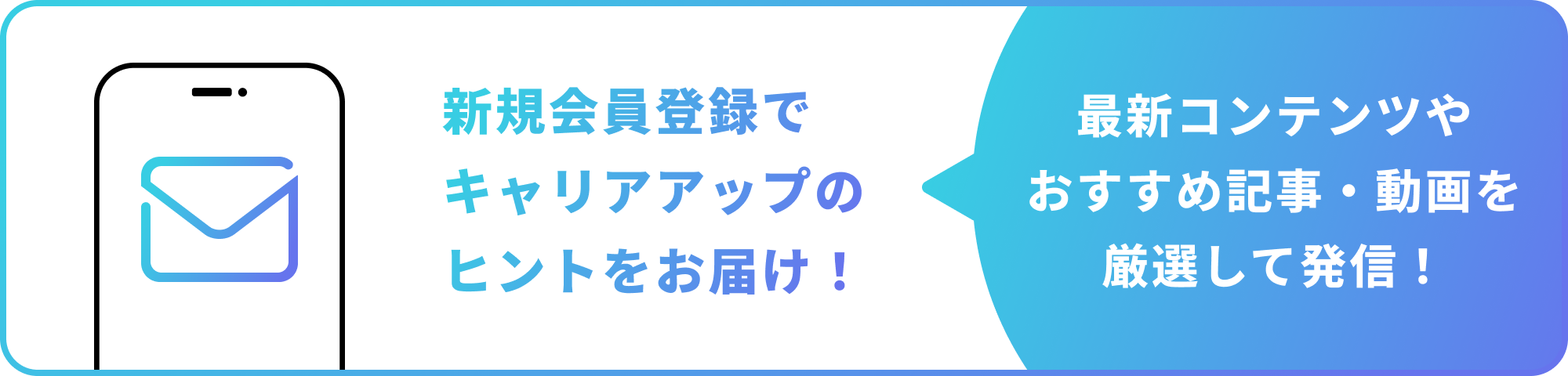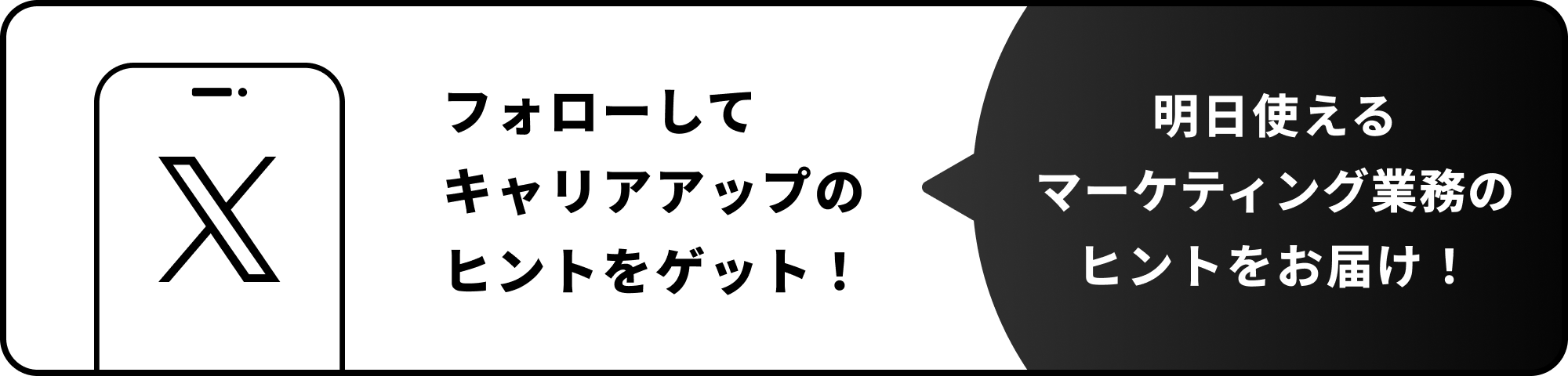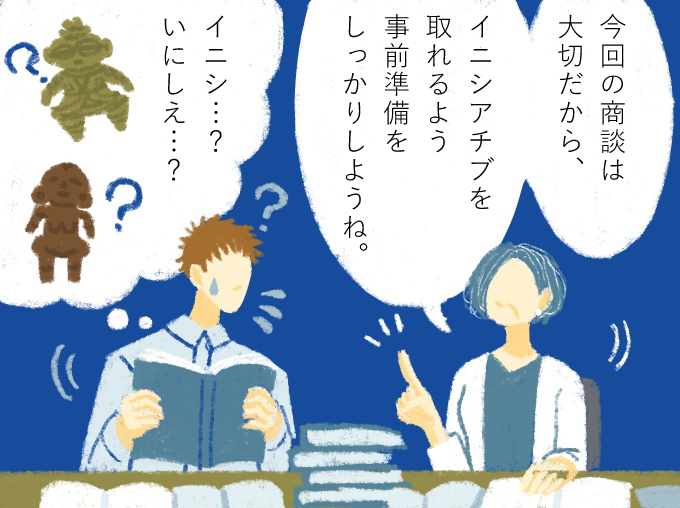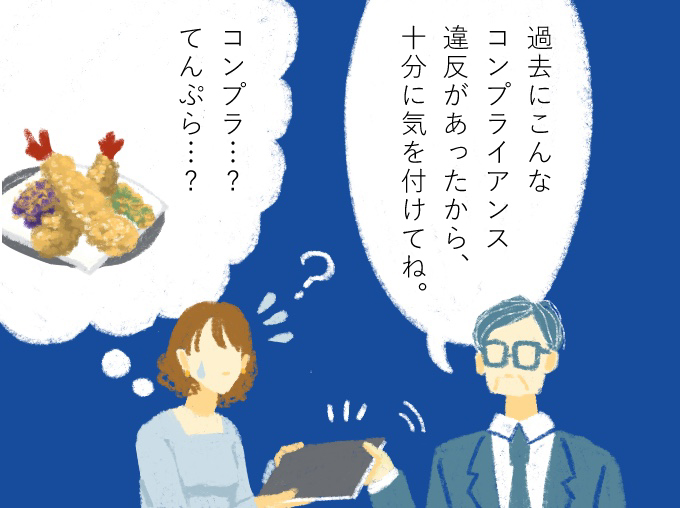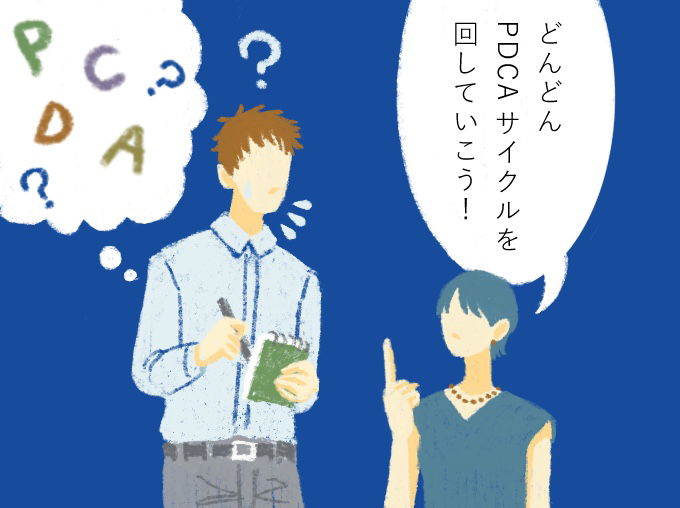
2024/02/28
PDCAサイクルとは?メリットや正しい活用方法、よくある失敗要因も解説!
PDCAサイクルとは、仮説の検証・実行を繰り返すことで業務改善を図るフレームワークのことをいいます。この記事では、PDCAサイクルのそれぞれのステップの役割や、メリット、よくある失敗要因について解説していきます。
PDCAサイクルとは?
PDCAサイクルとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の頭文字を取ったフレームワークのことをいいます。PDCAサイクルは、Planから順に始め、Actionまで終えたら最初のステップであるPlanに戻り、一連のプロセスを繰り返し行うことから、PDCAサイクルという名前が付けられています。
PDCAサイクルは業務品質や生産性の向上、効率化を図るために、ビジネスシーンで広く使われており、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?今回は、PDCAサイクルの各ステップやメリット、よくある失敗について詳しく解説します。PDCAサイクルをよく理解して業務に活かしましょう!
【おすすめ記事】スキルを磨きたいビジネスパーソンはこちらもチェック

PDCAは何の略…?
この施策はどんどんPDCAサイクルを回していこう!
(ぴ…?ぴーでぃー?何の略だ…?)
あ、PDCAね。PDCAっていうのは、英語のPlan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の頭文字を取ったフレームワークのことだよ。
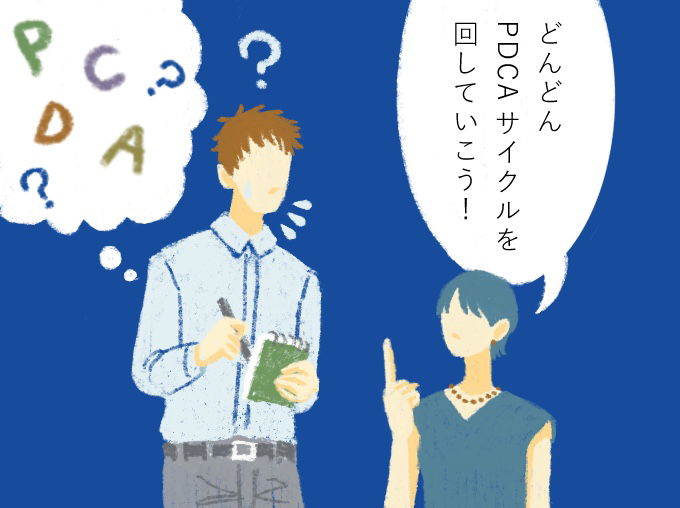
ビジネスの現場で、PDCAサイクルは度々使われるフレームワークですが、上手に使いこなすには、それぞれのステップをよく理解する必要があります。この記事では、よくある失敗例も紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
PDCAサイクルの由来
PDCAサイクルは、1950年代、アメリカの統計学者であり品質管理の父といわれるW・エドワーズ・デミングによって提唱されたフレームワークで、もとは製造業における生産・業務プロセスの改善や効率化を図るためのモデルとして活用されました。1950年、デミングが日本科学技術連盟に招待され、PDCAサイクルを提唱したことで、日本の製造業の品質が向上し、戦後の日本の経済成長を支えたといわれています。その後、製造業だけでなくビジネスシーンで広く使われるようになり、現在では品質管理だけでなく、ビジネスパーソンのセルフマネジメントメソッド(自己管理手法)としても使われています。
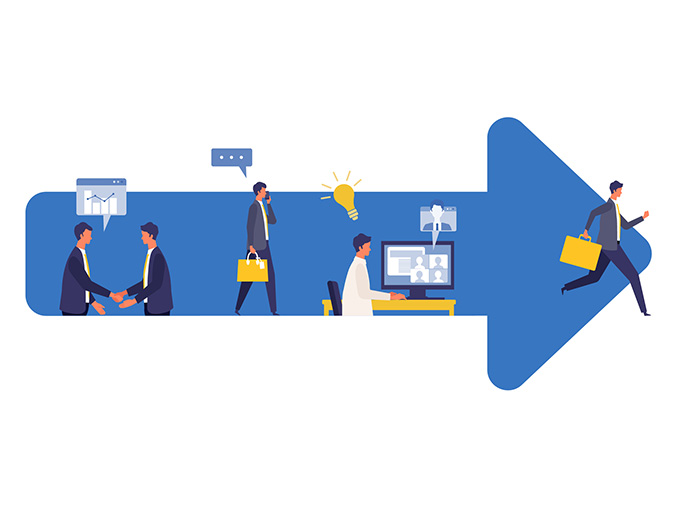
PDCAサイクルの4つのステップ
ここまでPDCAサイクルの概要や由来についてご紹介しました。次に、それぞれのステップで何をするのかを解説します。各ステップの役割をしっかり理解して、PDCAサイクルを使いこなせるようになりましょう。
Plan(計画)
Planでは、目標・目的を設定し、それらを達成するための具体的な計画を立てていきます。計画はなんとなく決めるのではなく、まずは現状を把握して課題を特定し、目標・目的の達成に向けて現実的かつ論理的なプランニングをすることが重要となります。
目標・目的を明確にしたら、5W1Hのwhen(いつ)、where(どこで)、who(誰が)、what(何を)、why(なぜ)、how(どのようにして)を意識して、できる限り具体的な実行計画を立てましょう。
また、Planでは特に下記2点がポイントです。
- 目標を定量で設けること
- 達成期限を明確にすること
定量目標を設けることで、より論理的に計画を立てやすくなります。また、達成期限を明確にすることで、現実的な計画であるかを確認することもできます。
Do(実行)
2つ目のステップであるDoでは、Planで立てた計画をタスクレベルに分解し、実行に移していきます。ここでの実行は、「計画に忠実に従う」というわけではなく、「ほかに効率がよい実行方法はないか」、「Planで想定した通りの結果になっているか」といった視点を持ちながら検証するという意味合いも含まれます。計画通りに進めることも大切ですが、当初の計画に固執し過ぎないようにしましょう。
また、Doでは、活動内容を記録するのがポイントです。うまくいったことだけではなく、計画通りに進まなかったことや実際にやってみるなかで生じた課題なども記録すると、計画と現状のギャップを把握することができ、後の工程で役立ちます。特に、データとして記録しておくと、次のCheckを客観的に行うことができるでしょう。
Check(評価)
3つ目のステップであるCheckでは、Planで設定した目標をどの程度達成できたのかや、計画の妥当性について評価します。このときに、なぜそのような結果になったのか、原因をしっかり分析して気付きや学びを得ることが最も大切です。特に、計画通りにいかなかった場合には、どこで計画が崩れてしまったのか、実施項目に過不足はなかったかというような点に注意して計画の妥当性を確認するのがポイントです。計画通りにいった場合も、成功要因の分析を忘れずに行いましょう。
また、主観に基づく評価は人によって捉え方が異なるため、データを用いたり、外部の視点を取り入れたりして、客観的かつ適切な分析ができるようにするとよいでしょう。
Action(改善)
最終ステップであるActionでは、Checkで行った分析結果をもとに、「ここをこうすれば次はうまくいくのではないか」というように、次のサイクルに向けた改善案の仮説を立てます。仮説が複数ある場合は、改善案を次のサイクルに活かすために、優先順位を付けて絞り込みましょう。また、次のサイクルでも引き続き行えるように、改善点だけでなく継続する点も併せて整理しておくとよいでしょう。

PDCAサイクルを活用するメリット
ここまで、PDCAサイクルのそれぞれのステップについて詳しくご紹介しました。ここからは、PDCAサイクルを活用するメリットを2つご紹介します。
目標達成力が強化される
前述した通り、PDCAサイクルの最初のステップであるPlanでは「目標・目的の明確化」をまず行い、達成のための計画を立てます。つまり、のちのステップでは常に目標・目的の達成を意識することになるので、PDCAサイクルを繰り返すことで目標達成力が強化されるでしょう。
また、目標と現実のギャップを意識するなかで、目標を立てる力自体も身に付きます。非現実的ではないけれど、たやすくもない適切な目標を立てることで、本質的な課題解決に向けた行動が明確になります。また、PDCAサイクルを上手に使いこなすことができると、目標や目的を達成することの喜びを感じることができ、モチベーションの向上にもつながるでしょう。
改善のノウハウが蓄積される
結果に対して要因を分析し、改善に向けた仮説立案を繰り返し行っていく過程で、計画や行動を改善するためのノウハウが蓄積されます。蓄積されたノウハウは、ものによってはほかのことに応用できたり、社内で共有できたりと、汎用的に使うことも期待できます。PDCAサイクルを繰り返すことで蓄積された改善ノウハウは、会社や個人にとって今後の財産となるでしょう。

PDCAサイクルのよくある失敗要因
PDCAサイクルに限らず、フレームワークはその本質を理解したうえで使うことが大切です。ここからは、4つのステップごとのよくある失敗要因をご紹介します。失敗例を参考にして、PDCAサイクルを上手に使いこなせるようになりましょう!
Plan(計画)の失敗要因
Planの失敗要因を2つご紹介します。1つ目は、目標を高く設定し過ぎてしまうことです。このことにより、Doの工程の精度が落ちてしまったり、なかなか目標を達成できずモチベーションの低下につながったりしてしまう恐れがあります。目標を立てる際には現状分析をしっかり行い、現実的な目標であるか見直しましょう。
2つ目は、目標達成までの計画が抽象的になっていることが挙げられます。この失敗を避けるには、目標達成までのプロセスを分解して考えることがおすすめです。目標を段階に分けたり、中間目標を立てたりと、プロセスを細かく検討していくことで、具体的な計画を立てることができます。
Do(実行)の失敗要因
Doの失敗要因として、Planに固執し過ぎてしまうことが挙げられます。前述した通り、DoはPlanで立てた計画を盲目的に実行すればよいのではなく、「ほかによいやり方はないか?」「このまま進めて目標は達成できるか?」といった視点を持ちながら検証していくことが大切です。Planに固執すると、本末転倒なので注意しましょう。
また、実行の記録をしていないことも失敗要因となります。後に正確な評価や分析を行うために、しっかり記録を付けておきましょう。
Check(評価)の失敗要因
Checkでよくある失敗要因は、評価基準が曖昧であることが挙げられます。評価基準が感覚的だと、正確な分析ができず、次のサイクルの効果が下がってしまいます。Checkのステップでどれだけ深く分析ができるかが、次のActionの質を左右するので、客観的に判断できる評価基準を設けるようにしましょう。
Action(改善)の失敗要因例
改善案の検討に時間をかけ過ぎてしまうのが、Actionでのよくある失敗要因です。PDCAサイクルは、何度も繰り返すことに意味があるため、サイクルがストップしてしまうと効果を発揮できません。完璧な1つの案を練ることに時間をかけるより、複数の案をスピーディーに立て、優先度を付けて早くPlanに進むようにしましょう。

PDCAサイクルを使いこなして成果につなげよう
これまで解説してきたように、PDCAサイクルは、仮説と計画を立て、それに基づき実行し、結果を検証することで次の新しい仮説を立てるという流れを繰り返すフレームワークです。改めてになりますが、PDCAサイクルを繰り返す目的は目標や目的の達成であり、PDCAサイクルというフレームワークを使うこと自体ではありません。
よくある失敗要因を振り返りながら、PDCAサイクルを使いこなして成果を生み出し、ビジネスパーソンとしてレベルアップしていきましょう!
📣 無料のリスキリングサービス『PERSOL MIRAIZ』
『PERSOL MIRAIZ』は、はたらくすべての人が利用できる無料のリスキリングサービスです。本来は高額なスキルの学習やキャリアカウンセリングを、誰でも気軽に始められます。
特長1:スキルの習得ができる学習コース
- 無料で利用できる
- 業界大手企業や著名人が提供・監修
- DXやマーケティング、エンジニアリングの領域が充実
特長2:プロが併走するキャリア相談
- 無料で利用できる(1時間のカウンセリング、30分の学習相談がそれぞれ5回)
- どんな職種や年代でもOK、話すことが整理しきれてなくてもOK
- 求人紹介はしない、転職ありきではないカウンセリング
特長3:身に付けたスキルが転職につながる
- PERSOL MIRAIZで身に付けたスキルを元に、パーソルキャリアが運営するdodaが転職まで伴走
- 急に求人を勧めたり、無理に転職を促すことはないので安心
この記事をシェア
ハッシュタグから記事を探す
カテゴリから記事を探す
トップランナーおすすめの良書
トップランナーが見た動画
インタビュー・対談
PERSOL MIRAIZのキャリアコンテンツ
キャリアに活かせる学習動画
トップランナーから、仕事に直結するスキルを学ぶ