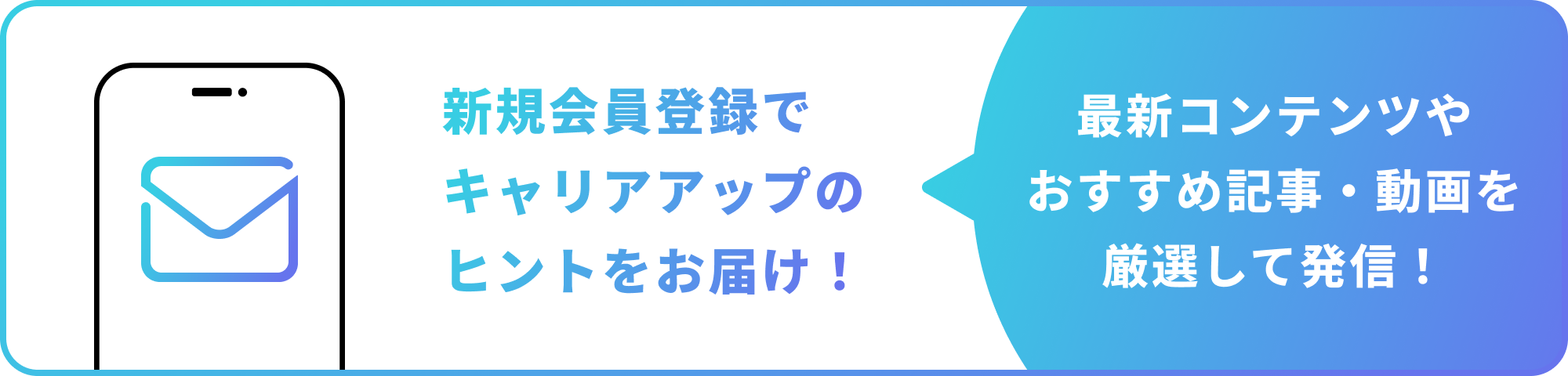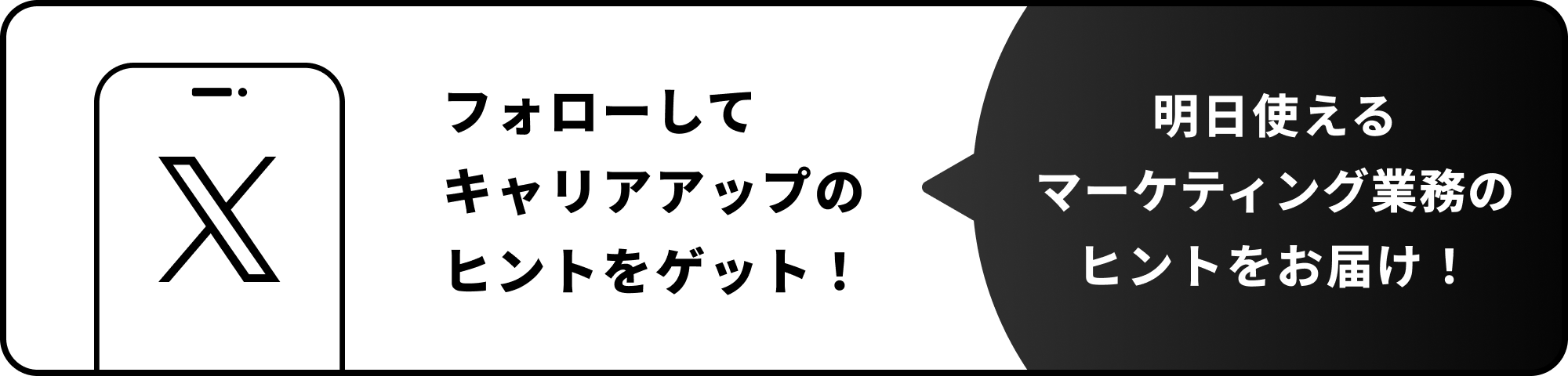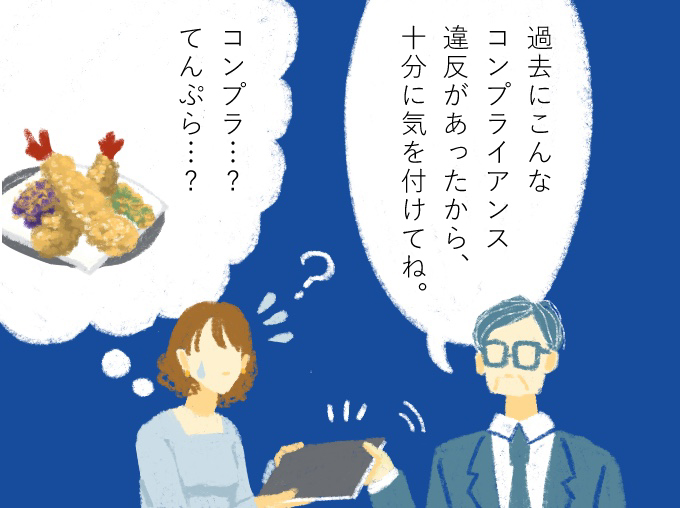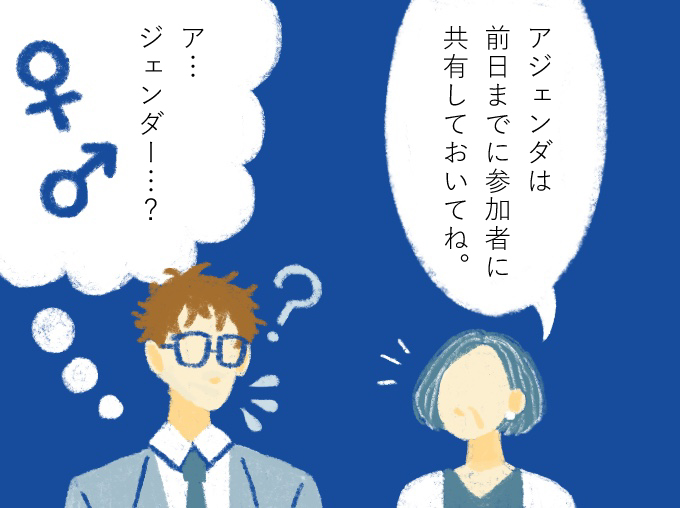2024/02/28
リテラシーとは?意味や種類、使い方などを徹底解説!
リテラシーとは読み書き能力を表す言葉で、ビジネスシーンでは、ある特定の分野における知識や理解、それを活用する能力のことを指します。この記事ではリテラシーの意味や種類、実際の使い方などをご紹介します。
リテラシーとは
リテラシーとは「読み書き能力」を表す「literacy」という英単語が語源の言葉です。日本では、ある特定の分野における知識や理解、それを活用する能力のことを指し、ビジネスシーンでは、一般的に「物事を適切に理解し活用する能力」といったニュアンスで使用されます。主な使い方としては、リテラシーが高い/低い、ある/ない、リテラシーを身に付ける/養う、といった風に使われます。
今回の記事では、リテラシーの意味やその種類、似た言葉との違いなどについて解説します。
【おすすめ記事】スキルを磨きたいビジネスパーソンはこちらもチェック

リテラシーとテレパシー?聞き間違いに注意
今年入った新卒入社の社員、学生時代に自分でアプリとか作ってたらしいですよ!
そうなんだ!ITリテラシーが高いんだね。
(テ…テレパシー…?)
リテラシーは、特定の分野への知識や理解、それらを活用する能力のことだよ。

リテラシーの種類
リテラシーは単体でも意味の通じる言葉ですが、分野ごとにさまざまな言葉と関連づいて使われます。ここでは、ビジネスシーンでよく使われるリテラシーを7つご紹介します。
ITリテラシー
ITリテラシーとは、ITを理解し、活用できる能力のことを指します。独立行政法人情報処理推進機構が定める『ITリテラシースタンダード(ITLS)』によると、ITリテラシーとは「社会におけるIT分野での事象や情報等を正しく理解し、関係者とコミュニケートして、業務等を効率的・効果的に利用・推進できるための知識、技能、活用力」と定義されています。※1 機械やITツールを適切に使いこなす力から、情報漏洩やウイルス感染を避けるためのセキュリティ理解力まで、非常に幅広い能力を指す言葉です。インターネットが普及した現代において、ITリテラシーの重要度は高まっています。
※1 出典:ITリテラシースタンダード IT Literacy Standard(ITLS)<初版>(独立行政法人情報処理推進機構)
情報リテラシー
情報リテラシーとは、目的に沿った情報を収集し、その情報を活用する能力のことです。総務省の通信白書では「情報機器の操作能力に加えて、情報を取り扱う上での理解、更には情報及び情報手段を主体的に選択し、収集活用するための能力と意欲」と記載されています。※2 情報リテラシーは、インターネットに限らず、新聞、本、人からの伝聞といった情報収集も含みます。ただ情報を集めるだけでなく、集めた情報を取捨選択して活用することが求められます。
※2 出典:平成10年版 通信白書(総務省)
メディアリテラシー
メディアリテラシーとは、新聞やテレビなどのメディアから得る情報を適切に取捨選択して活用する能力のことです。総務省によると、メディアリテラシーとは次の3つを構成要素とする複合的な能力のこととされています。※3
- メディアを主体的に読み解く能力
- メディアにアクセスし、活用する能力
- メディアを通じコミュニケーションする能力。特に、情報の読み手との相互作用的(インタラクティブ)コミュニケーション能力
世の中の情報のなかには、フェイクニュースや信ぴょう性の低いデータもたくさんあります。メディアからの情報をうのみにするのではなく、本当に正しいかどうか自身で調べ、考えることが大切です。
※3 出典:放送分野におけるメディアリテラシー(総務省)
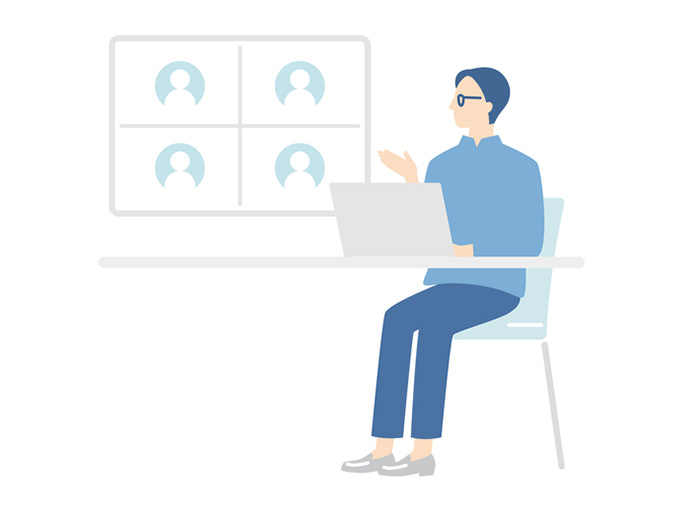
金融リテラシー
金融リテラシーとは、投資や金融など、お金に関する適切な知識を有し、活用する能力です。政府広報オンラインによると「金融リテラシーとは、経済的に自立し、より良い生活を送るために必要なお金に関する知識や判断力のこと」とされています。※4 金融リテラシーを高めるには、お金の管理方法や世界の経済状況、金融商品などについて学ぶ必要があります。金融リテラシーを身に付けることで、お金との適切な付き合い方を知ることができ、資産形成に活かすことができます。金融業界でない人も、新入社員のうちから身に付けておくとよいでしょう。
※4 出典:「金融リテラシー」って何?最低限身に付けておきたいお金の知識と判断力(政府広報オンライン)
インターネットリテラシー(ネットリテラシー)
インターネットリテラシー(ネットリテラシー)とは、インターネットの情報を正しく理解し、適切に活用できる能力のことです。インターネット上にある無数の情報の真偽を適切に判断し取り入れることや、肖像権や著作権などに配慮すること、他人を傷つける情報や誤った情報を発信しないことなどが求められます。
コンピューターリテラシー
コンピューターリテラシーとは、PCやスマートフォン、タブレットなどのIT機器を適切に扱うための知識や、応用能力を指します。Webの仕組みへの理解や、IT機器を使って求められている情報を素早く見つける力などもこのコンピューターリテラシーに含まれます。
ヘルスリテラシー
ヘルスリテラシーとは、自分の健康状態を理解し、健康を維持する力のことを指します。ビジネスに関係のない言葉に思えるかもしれませんが、体調を崩して仕事を休まないためにも、ヘルスリテラシーを高めることはビジネスパーソンには欠かせません。健康についての知識を深めることや医療制度を理解すること、自己管理能力を上げることでヘルスリテラシーを向上させましょう。
必要性が高まるITリテラシー
リテラシーの種類のなかでも特に需要が高まっているのが、ITリテラシーです。DX(デジタルトランスフォーメーション)が推進され、業務がデジタル化したことで、ビジネスシーンにおけるITの重要性が増しました。これからもさまざまな産業がITと結び付いていくことが考えられますが、需要に対してデジタルやITを使いこなせる人材は大きく不足しています。
経済産業省は「デジタル時代の人材政策に関する検討会」において、デジタル人材の育成が遅れていることを課題の1つに挙げました。2019年の経済産業省による試算では、「2030年にはデジタル人材が40~80万人の規模で不足が生じる懸念がある」と公表されるほど、日本のデジタル人材不足は深刻なものとなっています。※5 このように需要が高まっているITリテラシーを身に付けることで、ビジネスパーソンとしての市場価値を高めることができるでしょう。企業の研修制度やオンラインのセミナーへの参加だけでなく、個人でも勉強することでITリテラシーを身に付けることができます。
※5 出典:IT人材育成の状況等について(経済産業省)
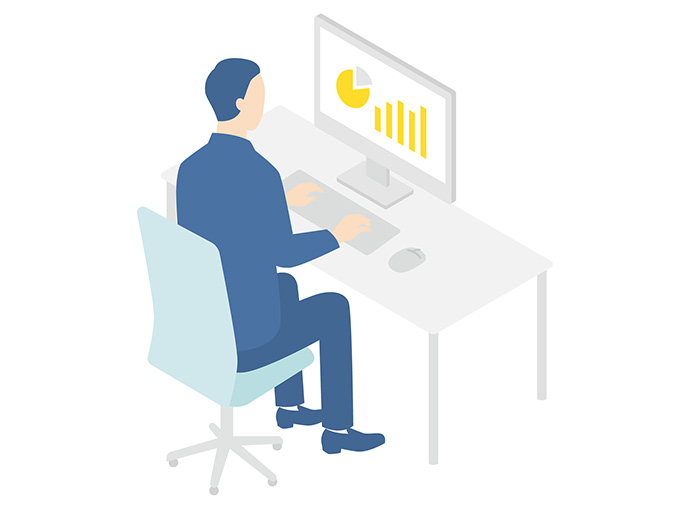
コンピテンシーとの違い
ビジネスの場でリテラシーと混同される言葉がコンピテンシーです。コンピテンシー(competency)とは、直訳すると「能力」、「適性」を意味する言葉で、ビジネスシーンでは優秀な成績を生み出す人に共通して見られる行動・能力適性を指します。職種、役割ごとに設定され、人事評価に活かされています。
リテラシーとコンピテンシーはどちらも能力に関する言葉ですが、何をもとにした能力であるかが異なります。リテラシーは知識を活用する能力のこと、コンピテンシーは行動、経験をもとに導かれた能力のことです。また、コンピテンシーは「コンピテンシーに基づいて人事評価を行う」といったように、あらかじめ定められた基準のような意味合いで使われることが多い一方、リテラシーは「○○さんはリテラシーが高い」といったように個人の能力に対して使われることが多い言葉です。こうした使い方の違いも注意しましょう。
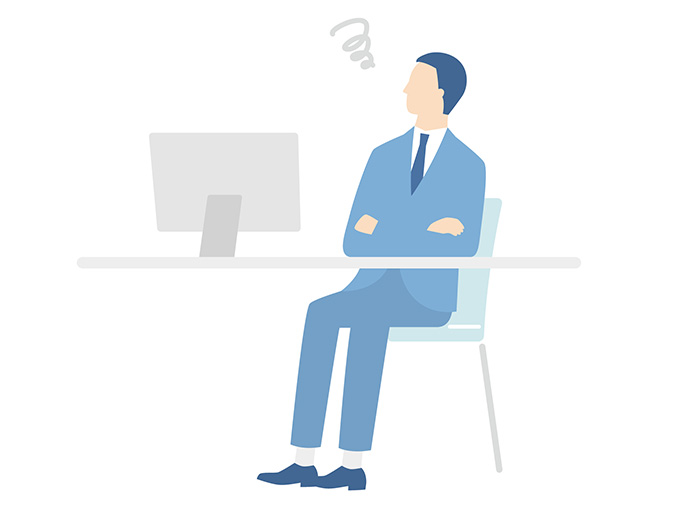
ビジネスシーンでの使い方と例文
リテラシーは、リテラシーが高い/低い、ある/ない、リテラシーを身に付ける/養う、といったように使われます。実際の例文を見ていきましょう。
<リテラシーの例文>
- ○○さんはITリテラシーが評価され、セキュリティ部門に配属されました
- 研修をしっかり取り組んで、メディアリテラシーを身に付けましょう
- ネットリテラシーを高めて、コンプライアンス違反を防ぎましょう
- 金融業界で働くからには、金融リテラシーを日々養ってください
それぞれの意味をしっかりと理解し、ビジネスシーンでも使えるようにしましょう。また、カタカナ語を使う際は、相手も理解している状態で使うことが大切です。相手がカタカナ語に慣れていない場合は、無理して使わず言い換えましょう。

リテラシーを高めよう
この記事では、リテラシーという言葉の意味やリテラシーの種類、使い方について解説しました。ITリテラシーやネットリテラシーが低いと、情報漏洩やSNSでの炎上といったコンプライアンス違反につながる恐れもあるので注意しましょう。また、リテラシーを身に付け、高めることは業務効率の改善や生産性の向上といったメリットもあります。
さらに、高いリテラシーを身に付けることができれば業務の幅が広がり、キャリアの選択肢が増えることも期待できます。社内研修といったリテラシーを高める機会が身の回りにある方は、ぜひ活用しましょう。
📣 無料のリスキリングサービス『PERSOL MIRAIZ』
『PERSOL MIRAIZ』は、はたらくすべての人が利用できる無料のリスキリングサービスです。本来は高額なスキルの学習やキャリアカウンセリングを、誰でも気軽に始められます。
特長1:スキルの習得ができる学習コース
- 無料で利用できる
- 業界大手企業や著名人が提供・監修
- DXやマーケティング、エンジニアリングの領域が充実
特長2:プロが併走するキャリア相談
- 無料で利用できる(1時間のカウンセリング、30分の学習相談がそれぞれ5回)
- どんな職種や年代でもOK、話すことが整理しきれてなくてもOK
- 求人紹介はしない、転職ありきではないカウンセリング
特長3:身に付けたスキルが転職につながる
- PERSOL MIRAIZで身に付けたスキルをもとに、パーソルキャリアが運営するdodaが転職まで伴走
- 急に求人を勧めたり、無理に転職を促したりすることはないので安心
この記事をシェア
ハッシュタグから記事を探す
カテゴリから記事を探す
トップランナーおすすめの良書
トップランナーが見た動画
インタビュー・対談
PERSOL MIRAIZのキャリアコンテンツ
キャリアに活かせる学習動画
トップランナーから、仕事に直結するスキルを学ぶ