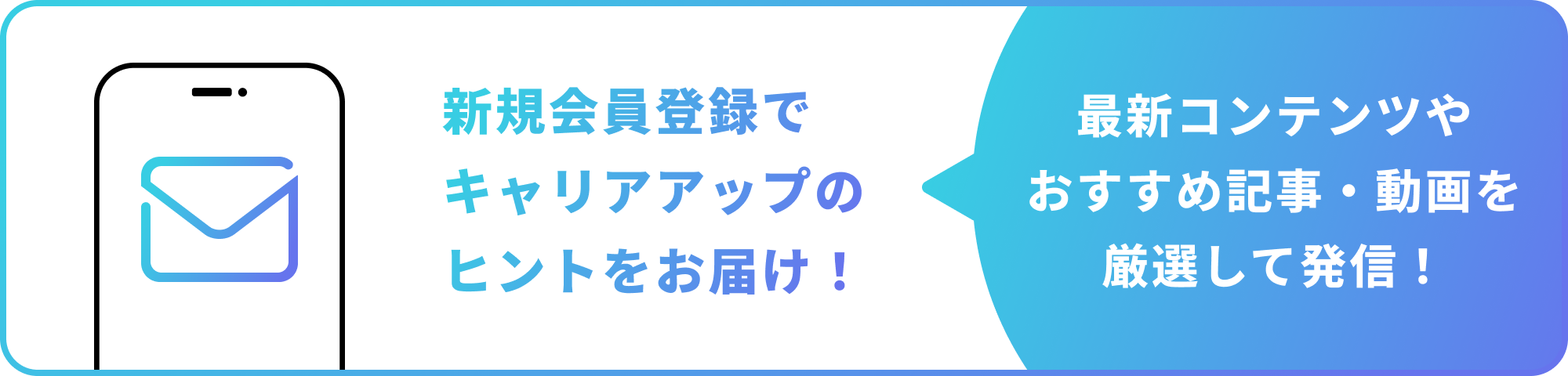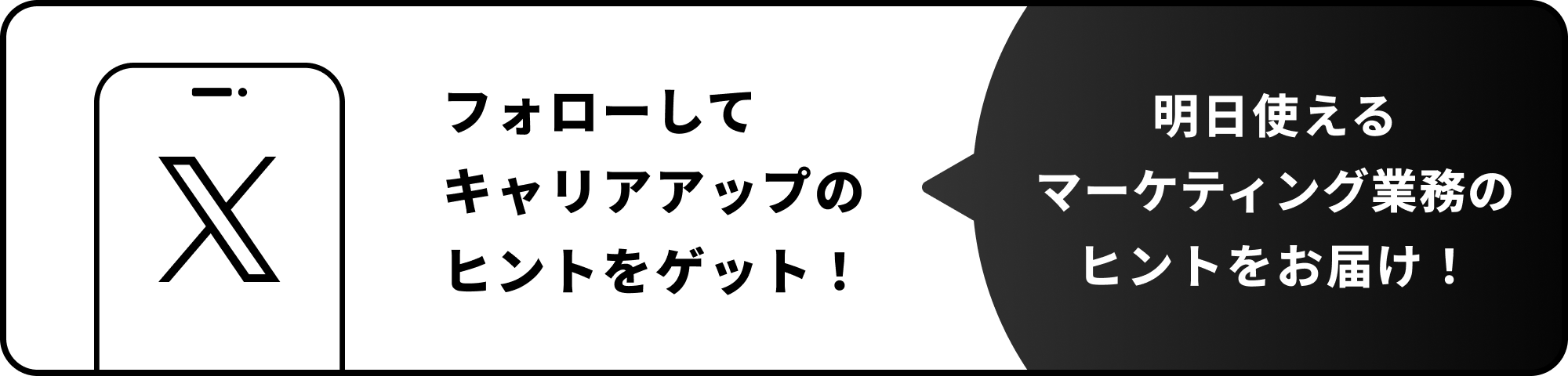2024/04/17
クリティカルとは?意味やビジネスシーンでの使い方について関連用語含め詳しく解説
クリティカルとは、「批判的な」「危機的な」「重大な」という意味を持つ言葉で、ビジネスシーンでもよく使われます。今回は、クリティカルの使い方や関連用語を紹介しつつ、クリティカルシンキングについて深く解説します。
クリティカルとは?
クリティカルの語源は英語の「critical」であり、「批判的な」、「決定的な」、「重大な」という意味を持ちます。さまざまな意味が含まれているため、実際どのように使われるのか知らない方もいるのではないでしょうか?今回は、クリティカルの関連用語に加えて、ビジネスに役立つクリティカルシンキングのメリットや鍛え方について解説します。
【おすすめ記事】スキルを磨きたいビジネスパーソンはこちらもチェック
クリティカルの意味って知ってる?どんな意味?
もしクリティカルな問題が発生したら、すぐに報告するように。
クリ…ヒカル…?
クリティカルとは「重大な」、「危機的な」という意味。あとは「批判的な」という意味もあって、クリティカルシンキング(批判的な思考)はよく使う言葉だよ。

業界や職場にもよりますが、「クリティカルな問題」という表現はビジネスシーンでよく登場します。「重大な問題」という意味合いで、緊急を要する状況であるため、言葉の意味を知らずに対応が遅れることがないよう、しっかり理解しましょう!
クリティカルを使った言葉
「クリティカルシンキング」や「クリティカルパス」など、クリティカルに関連した用語を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?ここからは、クリティカルを使った言葉についてジャンルを問わずご紹介します。
クリティカルシンキング
クリティカルシンキングとは、直訳すると「批判的思考」という意味になります。批判的思考とは、単に批判的に考えることを指すのではなく、主に「物事をうのみにせず、客観的な事実に基づき、批判的に分析して結論を得る手法」のことをいいます。これと似た用語であるロジカルシンキングは、「物事を体系的に整理し、論理的筋道を立てて考え結論を出す手法」の意味で使われることが一般的です。どちらも相反するものというわけではありませんが、クリティカルシンキングはロジカルシンキングとは異なり、前提条件や物事に対して疑いの視点を持つことが必要になります。
<例>
- 経験があっても、クリティカルシンキングで見直すことが大切だ
クリティカルパス
クリティカルパスとは、後の工程に影響を及ぼすタスクを抽出し、それぞれを結んだときに、最も期間の長い作業経路を指します。プロジェクトの最初の工程から最後の工程までを依存関係で結んでいくため、クリティカルパス上にある工程が1つでも遅延した場合、プロジェクト全体のスケジュールに大きく影響します。特に大きなプロジェクトでは、工程の数が多くなり、依存関係も複雑で確認するのが困難になるため、プロジェクトを遅延なく成功に導くにはクリティカルパスを事前に把握しておくことが大切です。
<例>
- リーダーからクリティカルパスの遅延が起こらないようにとの注意喚起があった
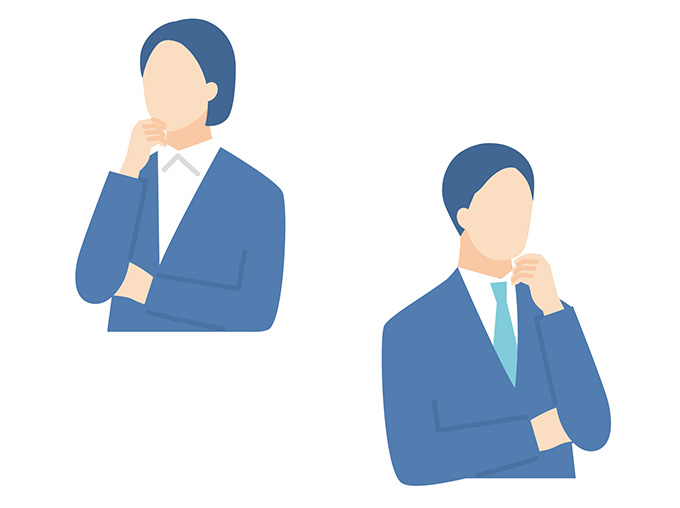
クリティカルマス
クリティカルマスとは、ある商品やサービスが爆発的に普及する分岐点を意味するマーケティング用語です。新たに市場に投入された商品やサービスは、まず先進者(イノベーター)に受け入れられ、その次に流行に敏感なアーリーアダプターと呼ばれる層に広まっていきます。ここまで普及した後は、一気に保守的な層まで浸透し、世間一般的に受け入れられていきます。この分岐点となる地点(アーリーアダプターまで広まった時点での普及率)がクリティカルマスです。クリティカルマスは、1962年に米国の社会学者であるエベレット・ロジャースの著書で初めて提唱され、通常クリティカルマスとされる普及率の指数は、市場の約16%であるといわれています。
<例>
- 新商品の現在の市場普及率は、クリティカルマスには届いていない状況だ
クリティカルエラー
クリティカルエラーとは、主にIT業界で用いられる用語で、コンピューターやソフトウェアが動作できないほどの致命的なエラー、危機的な状況のことを指します。前述の通り、クリティカルには批判的といった意味だけでなく、「重大な」、「危機的」なという意味合いもあります。
<例>
- 完成まであと少しのところで、コンピューターがクリティカルエラーを起こし、プロジェクトは中断された
クリティカルケア
医療業界では生命の危機に瀕している患者を看護することをクリティカルケアと呼ぶことがあります。クリティカルの「重大な」、「危機的な」という意味から考えると、クリティカルケアが上記の意味になるのも納得がいきますね。
<例>
- クリティカルケアが必要な患者を優先に処置を施した
クリティカルヒット
ビジネスシーンでは使うことは少ないかもしれませんが、クリティカルヒットという言葉があります。クリティカルヒットとは、主にゲームの戦闘中に使われる言葉で、相手に与える会心の一撃のことをいいます。雑学として覚えておくとよいでしょう。
<例>
- 敵から与えたクリティカルヒットによって、ゲームオーバーになった

クリティカルシンキングのメリット
ここまで、クリティカルに関連する用語についてご紹介しました。ここからは、ビジネスシーンでよく使うクリティカルシンキングについて深掘りしていきます。前述の通り、クリティカルシンキングとは「物事をうのみにせず、客観的な事実に基づき、批判的に分析して結論を得る手法」のことです。これは、目の前の事象に対して「なぜそうなったのか」「客観的な事実と相違ないか」といった疑問を繰り返し、物事の本質をつかもうとするプロセスだといえます。では、クリティカルシンキングを身に付けることにはどのような利点があるのか、1つずつ見ていきましょう。
前提条件にとらわれず事実や根拠に基づいた判断ができる
人間は、誰しも無意識のうちに考え方の癖や思い込み(バイアス)を持っています。これらは、生まれ育った環境や個々の経験によって形成されるものであり、それ自体は悪いことではありませんが、時に物事の本質を見極める際に障害となることがあります。クリティカルシンキングを鍛えることによって自らの先入観や主観を取り除き、ファクトに基づく判断ができるようになります。
問題解決力を高めることができる
物事を事実や根拠に基づいて分析するクリティカルシンキングは、その過程で矛盾や論理の飛躍、欠陥に気付くことができます。そのため、問題の解決策について検討する際に現実的な解決策を導き出し、優先度を把握することが可能になります。
新たな視点やアイデアを取り入れることができる
クリティカルシンキングをすることで、常識にとらわれず、前提や思い込みを取り除けられるため、これまで気が付けなかった新たな選択肢に出会える可能性があります。凝り固まった考えや概念にメスを入れることで、思わぬアイデアが生まれるきっかけとなるでしょう。

クリティカルシンキングの鍛え方
ここまで、クリティカルシンキングを身に付けることのメリットについてご紹介しましたが、クリティカルシンキングを鍛えるためには具体的にどのようなことが必要なのでしょうか?今後、クリティカルシンキングを仕事に活かしたい方のために、その鍛え方についてご紹介します。
前提条件や固定概念を疑う
クリティカルシンキングのメリットでもお伝えしたように、多くの人は個々の経験則に基づいた思い込み(バイアス)を持ち合わせています。そのため、「自分は、何らかのバイアスがかかった状態で物事を捉えている可能性がある」と意識することが大切です。過去の経験から自分が正しいと感じることでも、まずは疑いを持つことから始めましょう。
正しい情報を集める
クリティカルシンキングを行っても、誤った情報を元にしていれば最適解を導き出すことはできません。「この情報は正しいか?」というクリティカルシンキングで見直すことを心がけましょう。仕事においてはもちろんですが、現代社会は情報があふれているため、日常生活から情報の信ぴょう性や正確性を意識する癖を付けるのがおすすめです。
情報のデータや根拠を明確にする
先ほどお伝えした正しい情報を集めるためには、目の前の情報が正しいといえるエビデンスを取る癖を付けましょう。エビデンスとは、主にビジネスシーンで「根拠」、「裏付け」を意味する言葉です。きちんとエビデンスを取ることは、正しい情報かを見極めることに役立ちます。
仮説と検証を繰り返す
正確な情報を集めたら、それをもとに仮説を立てていきます。この際、必ず仮説と結果を照らし合わせて検証することが大切です。この仮説と検証のサイクルを繰り返せば、クリティカルシンキングの精度を上げることができるでしょう。

クリティカルシンキングを身に付けてビジネスに役立てよう
これまで、クリティカルの意味や関連用語、またクリティカルシンキングのメリットや鍛え方について解説してきました。特に環境の変化が目まぐるしい現代社会において、クリティカルシンキングを身に付けることは、ビジネスパーソンにとって非常に重要です。
AIやロボットなどのテクノロジーの進化をはじめ、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行、類を見ない異常気象の発生などは、これまでの常識が通じないほどの大きな変化が起きていることを物語っています。これから先も、もしかしたら、これまで成功していたことが今後は通用しなくなる可能性もあります。今回ご紹介したクリティカルシンキングを使って、日々変化する環境のなかでも本質を見失わないようにしましょう。ぜひこの記事を参考に、クリティカルシンキングを実践してみてくださいね!
📣 無料のリスキリングサービス『PERSOL MIRAIZ』
『PERSOL MIRAIZ』は、はたらくすべての人が利用できる無料のリスキリングサービスです。本来は高額なスキルの学習やキャリアカウンセリングを、誰でも気軽に始められます。
特長1:スキルの習得ができる学習コース
- 無料で利用できる
- 業界大手企業や著名人が提供・監修
- DXやマーケティング、エンジニアリングの領域が充実
特長2:プロが併走するキャリア相談
- 無料で利用できる(1時間のカウンセリング、30分の学習相談がそれぞれ5回)
- どんな職種や年代でもOK、話すことが整理しきれてなくてもOK
- 求人紹介はしない、転職ありきではないカウンセリング
特長3:身に付けたスキルが転職につながる
- PERSOL MIRAIZで身に付けたスキルをもとに、パーソルキャリアが運営するdodaが転職まで伴走
- 急に求人を勧めたり、無理に転職を促したりすることはないので安心
この記事をシェア
ハッシュタグから記事を探す
カテゴリから記事を探す
トップランナーおすすめの良書
トップランナーが見た動画
インタビュー・対談
PERSOL MIRAIZのキャリアコンテンツ
キャリアに活かせる学習動画
トップランナーから、仕事に直結するスキルを学ぶ