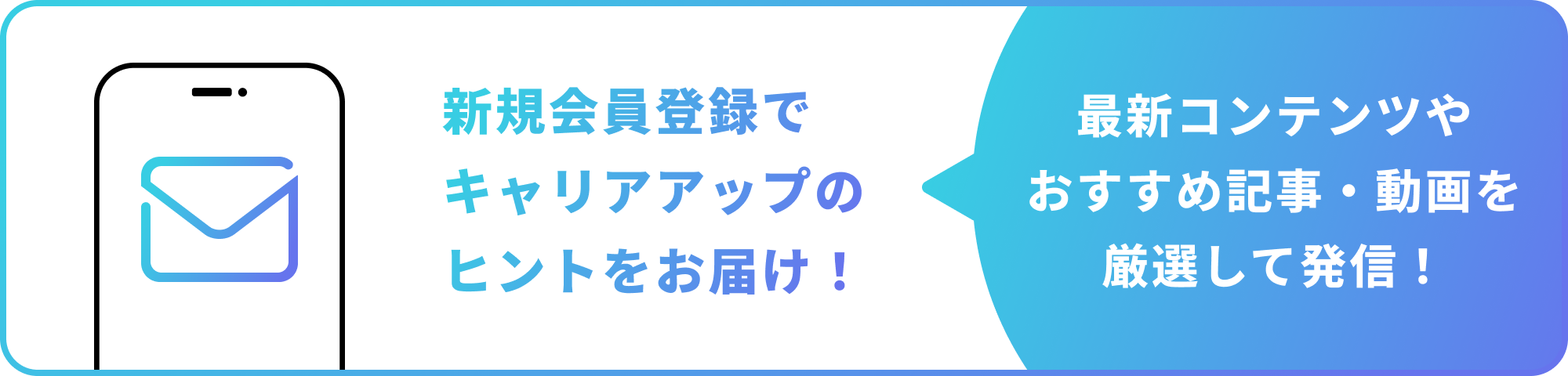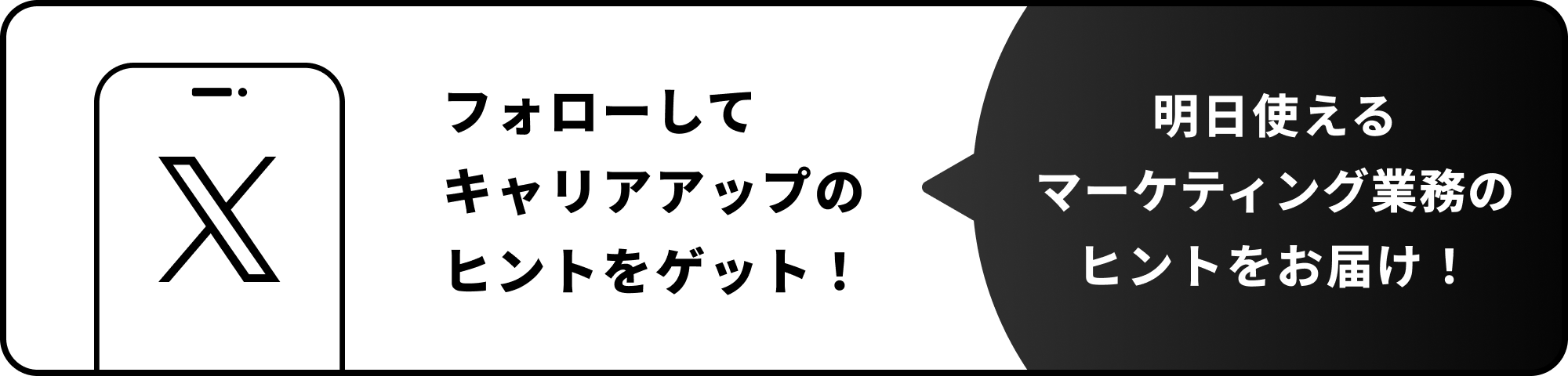2024/04/19
ナレッジとは?その意味や使い方、ノウハウやスキルとの違いも併せて解説
ナレッジとは、経験や学習を通して習得した知見や知識を意味する言葉で、ビジネスシーンでは付加価値のある情報や知見といったニュアンスが含まれます。ノウハウやスキルとは似て非なる言葉で、情報そのものに焦点を当てた言葉です。
ナレッジとは
ナレッジとは、英語の「knowledge」をカタカナ表記にした外来語で、経験や学習によって得られた「知見」や「情報」という意味を持ちます。本や新聞などの文章から得られる知識を指すことが多く、ビジネスシーンでは、付加価値のある知見、有益な情報といったニュアンスが強調されます。
【おすすめ記事】スキルを磨きたいビジネスパーソンはこちらもチェック
ナレッジって聞いたことある?ちょっと難しいビジネス用語
来週のミーティングで先輩からナレッジ共有があるからしっかりきいてね。
(ビレッジ…?)
ナレッジとは、知見や付加価値のある情報のことだよ。

ビジネスシーンで使うナレッジは、付加価値のある知見、有益な情報という意味です。ノウハウやスキルと混合しがちですが、次で詳しく説明するので正しく使いこなせるようにしましょう!
ナレッジと似た言葉との違い
ナレッジの意味を押さえたところで、それと似た言葉が浮かんできた方もいるのではないでしょうか?たとえば、ノウハウやスキルといった言葉は似たような意味合いですが、正確には異なります。以下ではそれらとナレッジとの違いをご紹介していきます。

ノウハウとの違い
ノウハウは、英単語の「know ‐ how」をカタカナ表記にした外来語です。それぞれの英単語の意味通り、何をどうすればよいか(how)を理解している(know)状態を指します。言い換えると、ノウハウは実践的な知識や知恵といった、問題に対してどのような知識を活用すれば解決できるか知っている状態のことです。
たとえば数学において、公式を知っていることはナレッジがある状態といえますが、その公式をどのような問題に活用できるか知らなければ、ノウハウがあるとはいえません。このように、ナレッジは経験や学習によって得られた情報そのものを指しますが、ノウハウはナレッジを物事の解決に向けて適切に活用できる能力を指すという点で異なります。
スキルとの違い
スキルは基本的に「技能」、「技術」といった意味で、訓練や学習によって獲得した専門的な能力を意味します。スキルの習得には、それに関わる知識と、知識を活用する知恵の両方が必要です。そのため、ナレッジとノウハウの両方を身に付けることでスキルを習得できるということになります。
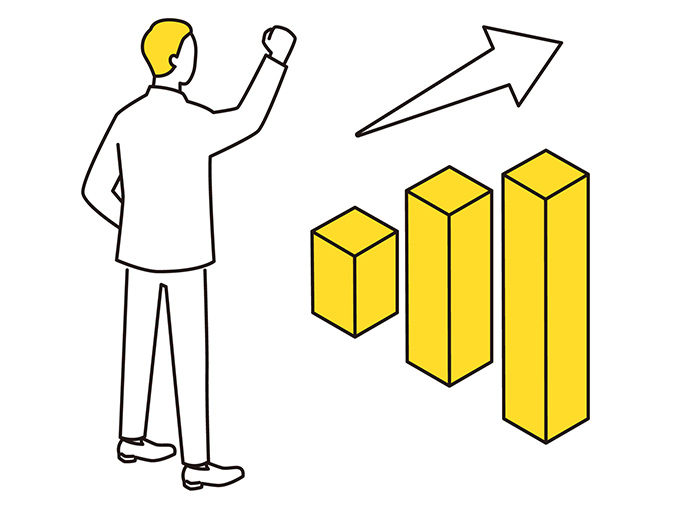
ナレッジの関連語
ここまで、ナレッジと混同しやすい用語についてご紹介してきました。以下ではナレッジにまつわる関連語を3つ解説していきます。
ナレッジマネジメント
ナレッジマネジメントとは、ナレッジ(付加価値のある知見、有益な情報)をマネジメント(管理)し、組織全体で共有することにより業務の効率化や生産性の向上を図る経営手法を指します。具体的には、ツールやメンター制度、社内会議などを活用しながら個人が持つナレッジを組織内で共有します。
ナレッジマネジメントは、主に「暗黙知」と「形式知」という2つの概念で成り立っています。暗黙知とは、個人の経験や勘に基づいた言語化しにくい主観的な知識であり、形式知とは暗黙知を言語や文章、数値や図表などを使って説明した知識を指します。
豊富なナレッジを持つ従業員がいるのは頼もしい一方で、その従業員しか業務を行えないというのは組織にとって好ましい状況ではありません。こうした、いわゆる「属人化」に陥らないためにも、ナレッジマネジメントをしっかりして従業員のナレッジのレベルをそろえることで、従業員が離職したり欠勤しても問題なく業務を遂行できるようになります。特に現代では、自らのステップアップのために転職をすることが一般的になり、人材の流動性が高まっています。組織力を高め、継続的な企業運営をするためにも、ナレッジマネジメントは重要といえるでしょう。
ナレッジマネジメントの基礎理論として、野中郁次郎氏らが示した「SECI(セキ)モデル」があります。SECIモデルとは、暗黙知をいかに形式知へと変換するかにとどまらず、既存の形式知と融合することで目的に沿った新たなナレッジを生み出すフレームワークを指します。
他人への伝え方が難しい暗黙知をいかに形式知に変換するか、生み出した形式知をいかに定着させる(内面化させる)かに焦点が定められているので、より効率的で実践的なナレッジマネジメントの実現が期待できます。
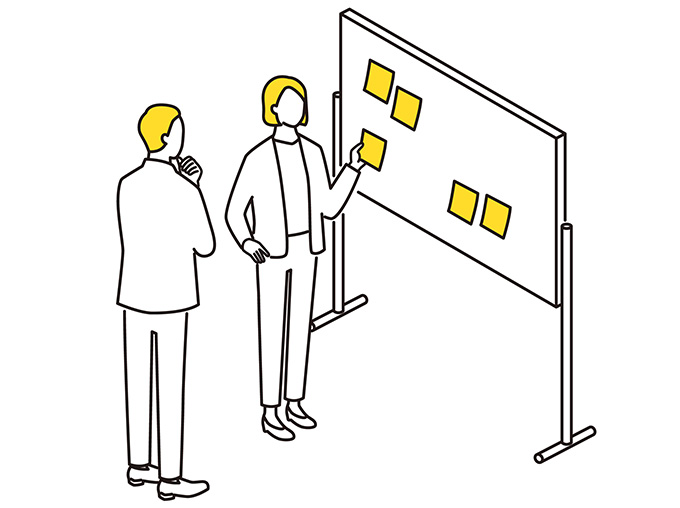
ナレッジベース
ナレッジベースとは、ナレッジとデータベースを合わせた造語で、必要なナレッジをすぐに取り出せるようにしたデータベースのことです。ツールを活用してナレッジベースを構築すれば、蓄積された情報に誰でも簡単にアクセスできるため、ナレッジマネジメントの効率化に役立つでしょう。
ナレッジワーカー
ナレッジワーカーとは、知的生産物を生み出す知識労働者のことで、知識や経験から新たな価値を生み出す労働者を意味します。エンジニアやコンサルタント、データサイエンティスト、マーケター、デザイナー、医師、弁護士などさまざまな職種が該当します。知的生産物とは、インプットしたナレッジをもとに生み出された生産物を指し、企画書や製品の設計図などが一例です。
ナレッジワーカーには、知識を習得する情報収集能力や、収集した情報をまとめる分析能力、分析をもとに新たなプロジェクトを効率よく行うためのノウハウをまとめるスキルなどが求められます。複雑化する現代社会において、0から1を生み出すナレッジワーカーは重宝されるでしょう。
一方、ナレッジワーカーに対してマニュアルワーカーという言葉が存在します。マニュアルワーカーとは、マニュアル通りに作業を行う労働者を指し、マニュアルで定められた業務を正確にこなす正確性と、効率的に業務を処理することのできるスピードが求められます。

ナレッジマネジメントのメリット
上記でもご紹介したナレッジマネジメントは、組織において多くのメリットがあります。ここでは、改めてそれらのメリットについてご紹介します。
人材育成に役立つ
ナレッジマネジメントは、効率的な人材育成に役立ちます。厚生労働省によると、人材育成は企業経営上の重要な課題の1つとされており、どの企業も特に注力している分野です。※1
人材育成の課題というと、新入社員や若手社員など若年層に関する課題と捉えられがちですが、中堅層をターゲットとした人材育成のほうが課題である場合もあります。というのも、中堅層の社員が人事異動した場合、若年層に比べて体系的な育成制度が整っていないことが多くあるためです。加えて、時間やノウハウがないといった若年層との共通の課題もあります。
しかし、こういった課題に対してナレッジマネジメントを導入することで、若年層にも中堅層にも体系的な育成制度の提供が可能になり、効率的な人材育成が期待できると考えられます。
※1 出典:「平成26年版 労働経済の分析」(厚生労働省)
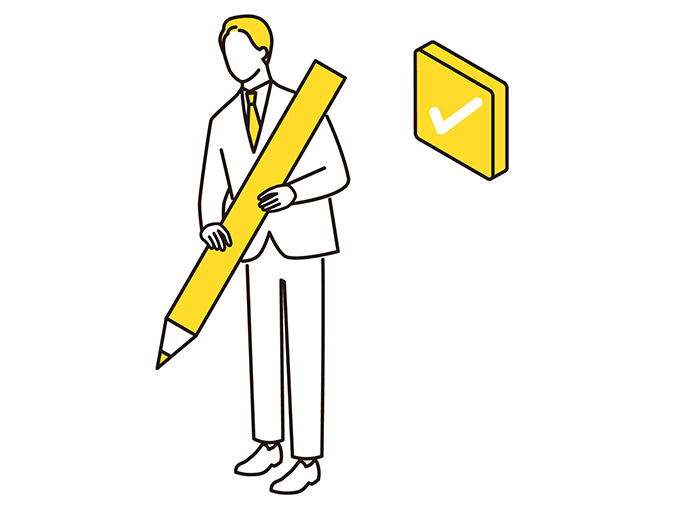
属人化の防止・解消
属人化とは、ある業務内容を特定の社員しか把握しておらず、ほかの社員へ業務の引き継ぎができない状態を指します。この場合、担当者の不在時は業務がストップしてしまう、退職時は後任者が一から試行錯誤する必要があるといった問題が生じます。
また、属人化している業務は暗黙知であることが多いため、客観的な評価や判断ができず、業務の正しさや効率性を検討する術もありません。その結果、作業効率が改善しないという問題が生じることもあります。ナレッジマネジメントを導入することで形式知に変換し、どの社員でも同じクオリティで業務が行えるようにすることで、円滑な企業運営が期待できるでしょう。
組織力の強化
各々のナレッジを組織全体で共有することで、従業員それぞれのレベルが底上げされ、結果的に業績の向上が期待できます。また、過去に起きたミスとその対応策を記録しておけば、同様のミスが起きた場合に迅速に解決できるなど、作業の効率化という面でもナレッジマネジメントは効果的です。

ナレッジを蓄積・活用してスキルアップ!
ここまで、ナレッジの意味やビジネスシーンにおける活用例などについて解説してきました。社内に蓄積されたナレッジをうまく活用すれば、自身の成長スピードが早まり、スキルアップにもつながります。社内ポータルサイトのようなナレッジ共有ツールを導入している企業もあるので、自社のナレッジ共有の仕組みを確認してみるのもよいでしょう。まずは自分のナレッジをきちんと整理したり、足りないものは吸収したりして、スキルアップを目指しましょう!
📣 無料のリスキリングサービス『PERSOL MIRAIZ』
『PERSOL MIRAIZ』は、はたらくすべての人が利用できる無料のリスキリングサービスです。本来は高額なスキルの学習やキャリアカウンセリングを、誰でも気軽に始められます。
特長1:スキルの習得ができる学習コース
- 無料で利用できる
- 業界大手企業や著名人が提供・監修
- DXやマーケティング、エンジニアリングの領域が充実
特長2:プロが併走するキャリア相談
- 無料で利用できる(1時間のカウンセリング、30分の学習相談がそれぞれ5回)
- どんな職種や年代でもOK、話すことが整理しきれてなくてもOK
- 求人紹介はしない、転職ありきではないカウンセリング
特長3:身に付けたスキルが転職につながる
- PERSOL MIRAIZで身に付けたスキルをもとに、パーソルキャリアが運営するdodaが転職まで伴走
- 急に求人を勧めたり、無理に転職を促したりすることはないので安心
この記事をシェア
ハッシュタグから記事を探す
カテゴリから記事を探す
トップランナーおすすめの良書
トップランナーが見た動画
インタビュー・対談
PERSOL MIRAIZのキャリアコンテンツ
キャリアに活かせる学習動画
トップランナーから、仕事に直結するスキルを学ぶ